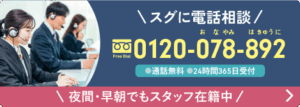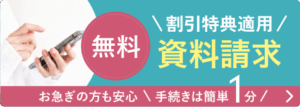突然の訃報に際し、ご心痛のことと深くお察し申し上げます。大切なご家族がお亡くなりになり、深い悲しみの中、これから葬儀の準備を進めなければならない状況に、大きな不安を感じていらっしゃることと存じます。
特に近年増えている「家族葬」は、いざ執り行うとなると「どのような流れで進むのだろう」「日程はどれくらいかかるのだろう」と、わからないことばかりではないでしょうか。
この記事では、ご逝去から葬儀を終えるまでの家族葬の一般的な流れと日程について、初めての方にも分かりやすく解説します。各ステップでご遺族が何をすべきかを具体的に説明しますので、今後の見通しを立てる一助となれば幸いです。
家族葬とは?一般葬との違い

近年、葬儀の形式として「家族葬」を選ぶ方が増えています。言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのような葬儀なのか、一般葬と何が違うのか、詳しくご存じない方も多いかもしれません。まずは、家族葬の基本的な知識について解説します。
家族だけで見送る小規模な葬儀
家族葬とは、その名の通り、ご家族やごく親しい親族、故人と特に親交の深かった友人など、参列者の範囲を限定して行う小規模な葬儀のことです。参列者の人数に明確な定義はありませんが、30名以下で行われることもあります。
家族葬の最大の特徴は、親しい人たちだけで、故人との最後のお別れの時間をゆっくりと過ごせる点です。一般葬のように多くの弔問客への対応に追われることが少ないため、精神的な負担が軽減され、心ゆくまで故人を偲ぶことができます。
家族葬と一般葬の主な違い
家族葬と一般葬の基本的な儀式(お通夜、告別式、火葬)の流れに大きな違いはありません。最も異なるのは「参列者の範囲」と、それに伴う「葬儀の規模」です。
以下の表で主な違いを確認してみましょう
項目 | 家族葬 | 一般葬 |
参列者の範囲 | 家族、親族、親しい友人など限定的 | 家族、親族、友人、会社関係者、近所の方など広い |
参列人数 | 〜30名程度 | 50名〜100名以上になることも |
訃報の連絡 | 参列をお願いする方のみに連絡 | 関係各所に広く知らせる |
特徴 | 故人とゆっくりお別れができる | 故人と縁のあった多くの方々でお見送りできる |
費用 | 比較的抑えられる傾向 | 参列者の人数に応じて高くなる傾向 |
【関連記事】
家族葬 20 人の費用相場は?追加料金で後悔しないための内訳と注意点を解説します | 家族葬のそうえん【公式】 | 東京都日野、町田の葬儀社 | 多摩地区クチコミ評価No.1
家族葬を 5 人で行う費用はいくら?平均相場と内訳、安く抑える 7 つの方法を解説します
家族葬の一般的な流れと日程

ご家族が亡くなられてから葬儀が終わるまで、ご遺族は限られた時間の中で多くのことを決定し、準備を進める必要があります。
ここでは、ご逝去された日を1日目として、3日間の流れと日程のモデルケースを時系列で解説します。
手順1:ご逝去当日(1日目)に行うこと
ご逝去当日は、悲しみの中で様々なら手続きを迅速に進めなければなりません。まず、医師から「死亡診断書」を受け取ります。この書類は後の手続きで必ず必要になるため、大切に保管してください。
次に、ご遺体を安置する場所へ搬送してもらうため、葬儀社へ連絡します。事前に葬儀社を決めていればスムーズですが、決まっていなくても病院が提携している葬儀社を紹介してくれる場合もあります。ご遺体の安置場所は、ご自宅か斎場の安置施設が一般的です。
ご遺体を安置した後、葬儀社と具体的な打ち合わせを行います。この打ち合わせで、喪主の決定、葬儀の日程や場所、内容、費用などを決めていきます。
時間 | 主な内容 | ご遺族が行うこと |
ご逝去直後 | 死亡診断書の受け取り | 医師から受け取り、大切に保管する |
随時 | 葬儀社への連絡・搬送 | 葬儀社に連絡し、ご遺体の搬送を依頼する |
搬送後 | ご遺体の安置 | 自宅または斎場の安置施設にご遺体を安置する |
安置後 | 葬儀社との打ち合わせ | 喪主、日程、場所、葬儀内容、費用などを決める |
打ち合わせ後 | 関係者への連絡 | 家族葬に参列をお願いする方へ訃報と日程を連絡する |
手順2:お通夜(2日目)の流れ
お通夜は、ご逝去の当時~翌日の夕方に行われるのが一般的です。故人と親しい人々が集まり、夜通し灯りを絶やさずに寄り添い、別れを惜しむ儀式です。 お通夜が始まる前に、故人のお体を清め、死装束を整えて棺に納める「納棺の儀」を執り行います。ご家族にとっては、故人のお体に触れることができる最後の機会となります。
お通夜では、僧侶による読経、喪主からの焼香、そして参列者の焼香と進みます。家族葬では参列者が少ないため、焼香の時間は比較的短く済みます。お通夜の後には、「通夜振る舞い」として食事の席が設けられることがありますが、家族葬では省略されたり、ごく内輪だけで済ませたりすることも増えています。
【関連記事】家族葬で通夜なしの流れを解説!費用やマナー、後悔しないための注意点 | 家族葬のそうえん【公式】 | 東京都日野、町田の葬儀社 | 多摩地区クチコミ評価No.1
手順3:告別式から火葬(3日目)の流れ
お通夜の翌日、葬儀・告別式が執り行われます。告別式は、故人との最後の別れの儀式です。 お通夜と同様に、僧侶の読経と焼香が行われます。
その後、ご遺族や参列者で棺の中に花を入れ、故人と最後のお別れをする「お花入れの儀」を行います。告別式が終わると、棺を霊柩車に乗せ、火葬場へと向かいます(出棺)。火葬場では、最後の読経と焼香を行う「納めの式」の後、火葬となります。
火葬には1時間〜2時間ほどかかり、ご遺族は控室で待機します。 火葬が終わると、ご遺骨を骨壷に納める「お骨上げ(収骨)」を行い、一連の儀式は終了となります。
【関連記事】葬儀後のアフターサポート | 家族葬のそうえん【公式】 | 東京都日野、町田の葬儀社 | 多摩地区クチコミ評価No.1
家族葬の日程を決める際のポイント

家族葬の日程は、ご遺族の希望だけで決められるわけではありません。法律の定めや、関係者の都合など、いくつかの要素を考慮して決定する必要があります。
法律で定められた火葬までの日数
日本の法律(墓地、埋葬等に関する法律)では、「死後24時間を経過した後でなければ火葬してはならない」と定められています。
これは、万が一の蘇生の可能性を考慮したものです。そのため、どれだけ急いでも、亡くなった当日に火葬を行うことはできません。最短でもご逝去の翌日以降となります。
参考:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号) |厚生労働省
火葬場や僧侶の都合を確認する
葬儀の日程を決める上で最も重要なのが、火葬場の空き状況です。特に都市部では火葬場が混み合っており、希望の日時に予約が取れないこともあります。火葬場の予約が取れないと、葬儀全体の日程が後ろにずれることになります。
また、菩提寺がある場合や、読経を依頼する僧侶がいる場合は、その僧侶のスケジュール確認も必須です。これらの関係各所の都合をすり合わせながら、最適な日程を葬儀社と相談して決めていきます。
確認事項 | 内容 | 注意点 |
火葬場の空き状況 | 希望する日時に火葬が可能か | 年末年始や友引の翌日は混雑しやすい |
僧侶の都合 | 読経を依頼する僧侶の予定 | 菩提寺がある場合は必ず最初に相談する |
参列者の都合 | 遠方に住む親族などが間に合うか | 特に参列してほしい方には早めに連絡し予定を確認する |
斎場(式場)の空き | お通夜・告別式を行う会場が使えるか | 火葬場併設の斎場は人気が高い |
友引など六曜は気にするべきか
カレンダーに記載されている「友引」の日に葬儀を行うと、「友を冥土に引き寄せる」とされ、縁起が悪いと考える風習があります。このため、友引の日を休業日にしている火葬場が全国的に多くあります。
ただし、これは仏教の教えとは関係のない民間の風習です。ご遺族や親族が気にしないのであれば、友引に葬儀を行っても問題はありません。しかし、火葬場が休みで物理的に行えない場合があるため、注意が必要です。
家族葬で後悔しないための注意点

家族葬は親しい人だけで心温まるお見送りができる一方、参列者を限定するからこそ、周囲への配慮が重要になります。
後々トラブルにならないためにも、いくつか注意すべき点があります。
参列者の範囲を明確に決める
家族葬を行うにあたり、最初に「どこまでの範囲の方にお声がけをするか」をご家族でしっかりと話し合って決めることが大切です。故人の交友関係を思い返し、ご遺族だけで判断が難しい場合は、親族にも相談しましょう。
一度決めた方針は、後から変更すると混乱を招く原因になります。「あちらの親戚は呼んだのに、うちは呼ばれなかった」といった不満が出ないよう、明確な基準を持って一貫した対応を心がけることが重要です。
訃報連絡で家族葬である旨を伝える
参列をお願いする方へ訃報を連絡する際には、必ず「故人の遺志により、葬儀は家族葬にて執り行います」とはっきりと伝えましょう。これにより、連絡を受けた方が「自分以外に誰に知らせるべきか」と悩むのを防ぐことができます。
また、参列をご遠慮いただく方々へは、葬儀が終わった後に報告の挨拶状を送るのが一般的です。会社の同僚など、どうしても事前に伝えなければならない場合は、家族葬であることと、参列や香典は辞退する旨を明確に伝える配慮が必要です。
香典や供花の辞退を伝える方法
家族葬では、ご遺族の負担を減らすために香典や供花、供物を辞退するケースも見られます。辞退する場合は、その意向を曖昧にせず、明確に伝えることがマナーです。訃報連絡の際に、「誠に勝手ながら、御香典、御供花、御供物の儀は固くご辞退申し上げます」といった言葉を添えてお伝えしましょう。
それでも、弔意を示したいと持参される方もいらっしゃるかもしれません。その際は、一度は感謝を述べた上でお断りし、それでも強く希望される場合は、ご厚意として受け取るなど、臨機応応な対応も必要です。
家族葬にかかる費用相場

葬儀にかかる費用は、大きな心配事の一つです。家族葬は一般葬に比べて費用を抑えられる傾向にありますが、具体的にどのようなことにお金がかかるのでしょうか。
【関連記事】【家族葬の費用】相場と内訳を徹底解説!賢く安くする方法も紹介
家族葬の費用の内訳
家族葬の費用は、主に以下の3つの要素で構成されています。葬儀社に支払う費用だけでなく、飲食費や寺院へのお布施なども含めて総額を考えることが大切です。
費用の種類 | 主な内訳 | 費用の目安 |
葬儀一式の費用 | 祭壇、棺、遺影、搬送費、人件費など | 約30万円~70万円 |
飲食接待費 | 通夜振る舞いや精進落としの食事代、返礼品代 | 約10万円~30万円 |
寺院費用 | 読経や戒名に対するお布施 | 約10万円〜35万円(宗派や寺院による) |
※上記の金額はあくまで目安です。
費用を抑えるためのポイント
故人をしっかりとお見送りしつつ、費用をできるだけ抑えたいと考えるのは自然なことです。費用を抑えるためには、いくつかのポイントがあります。
まず、葬儀プランの内容をよく確認し、不要なオプションは外すことが大切です。例えば、立派すぎる祭壇や棺を選ばない、通夜振る舞いを簡素にする、といった工夫が考えられます。複数の葬儀社から見積もりを取り、内容と費用を比較検討することも、納得のいく葬儀を行うために非常に重要です。
信頼できる葬儀社の選び方

葬儀は、やり直しがきかない大切な儀式です。だからこそ、信頼できる葬儀社をパートナーに選ぶことが、後悔のないお見送りのためには不可欠です。
複数の葬儀社から見積もりを取る
葬儀社を選ぶ際は、1社だけで決めるのではなく、複数の葬儀社から見積もりを取ることをお勧めします。見積もりを比較することで、費用の相場観が分かり、それぞれの葬儀社のサービス内容の違いも明確になります。
見積もりを依頼する際は、できるだけ同じ条件(参列人数、斎場の希望など)を伝えると、比較がしやすくなります。見積書の内容で不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。曖昧な回答をしたり、説明が不十分だったりする葬儀社は避けた方が賢明です。
チェックポイント | 確認する内容 |
見積もりの明確さ | 「一式」ではなく、項目ごとに詳細な記載があるか |
追加費用の可能性 | 見積もり以外に追加で発生する可能性のある費用について説明があるか |
プラン内容 | 必要なものが含まれているか、不要なものはないか |
支払い条件 | 支払い方法や期日はいつか |
事前相談を活用して担当者と話す
もし時間に余裕があれば、葬儀社の「事前相談」を活用することをお勧めします。実際に担当者と顔を合わせて話をすることで、その葬儀社の雰囲気や担当者の人柄を知ることができます。
こちらの不安や要望に親身になって耳を傾け、専門的な立場から的確なアドバイスをくれる担当者であれば、安心して大切な葬儀を任せることができるでしょう。
ご逝去後は心身ともに余裕がなくなるため、元気なうちに相談しておくことで、いざという時に慌てずに行動できます。
【関連記事】事前相談の重要性とは | 家族葬のそうえん【公式】 | 東京都日野、町田の葬儀社 | 多摩地区クチコミ評価No.1
葬儀後に行う手続きと法要

葬儀が終わっても、ご遺族にはまだやるべきことがあります。様々な行政手続きや、故人を供養するための法要が続きます。
葬儀後に行う主な行政手続き
葬儀後は、役所や金融機関などで様々な手続きが必要になります。期限が設けられているものも多いため、計画的に進めましょう。
手続きの種類 | 提出先 | 期限の目安 |
年金受給停止手続き | 年金事務所 | 死亡後10日または14日以内 |
世帯主の変更届 | 市区町村役場 | 死亡後14日以内 |
健康保険の資格喪失届 | 国民健康保険:市区町村役場 社会保険:事業主が日本年金機構 | 国民健康保険:死亡後14日以内 社会保険:死亡後5日以内(事業主が提出) |
相続放棄 | 家庭裁判所 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
所得税の準確定申告 | 税務署 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
この他にも、運転免許証の返納、パスポートの失効手続き、金融機関の口座名義変更・解約など、多岐にわたる手続きがあります。
四十九日法要までの流れ
仏教では、故人が亡くなってから49日目に、来世の行き先が決まる大切な日とされています。この日に行うのが「四十九日法要」です。
ご遺族は、この日に向けて寺院や親族と日程を調整し、会場や会食の手配を進めます。法要当日は、親族で集まり、僧侶の読経の後、会食をするのが一般的です。この四十九日法要をもって、忌明けとなります。
また、この法要に合わせてお墓に遺骨を納める「納骨式」を執り行うことも多いです。
まとめ

家族葬は、ご家族や親しい方々だけで、故人との最後の時間を大切に過ごすことができる葬儀形式です。ご逝去から葬儀が終わるまでの一般的な流れは3日間ほどですが、火葬場の状況やご遺族の希望によって日程は変動します。
大切なのは、限られた時間の中で慌ててしまわないよう、事前に全体の流れを把握しておくことです。この記事が、深い悲しみの中にいるご遺族の不安を少しでも和らげ、故人を心安らかにお見送りするための一助となれば幸いです。
「そうえん倶楽部」の生前会員制度なら、資料請求するだけで特別割引が自動適用されます!年会費・更新費・積立金は一切不要で、二親等のご親族まで追加料金なしでご利用可能です。簡単 1 分の資料請求で、安心の葬儀準備を始めませんか?
スマホの場合は、電話での問い合わせも可能です。特にお急ぎの方はお電話でお気軽にご相談ください。

厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
遺体感染管理士出身の新潟で広告業などを経験し、出産・子育てを経て東京へ移住。
縁あって出合った司会の仕事をきっかけに葬儀業界へ、年間300件のお別れに立ち会い、2021年、株式会社 葬援の取締役に就任。