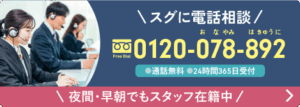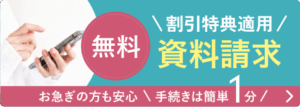ご家族が亡くなられた直後、悲しみの中で葬儀の準備を進めることは、精神的にも体力的にも大きな負担となります。近年、故人と近しい親族のみでゆっくりとお別れができる「家族葬」を選ぶ方が増えていますが、「故人が慣れ親しんだ自宅から送り出してあげたい」という想いから、自宅での家族葬を検討される方もいらっしゃいます。
この記事では、自宅で家族葬を行う場合のメリット・デメリット、具体的な流れや費用、そして後悔しないための注意点について、分かりやすく解説します。不安な気持ちを抱えている方が、少しでも安心して準備を進められるよう、必要な情報をお届けします。
自宅での家族葬とは?故人と心ゆくまでお別れする選択肢

自宅での家族葬とは、その名の通り、故人が住み慣れたご自宅を式場として執り行う、少人数のお葬式のことです。かつては自宅で葬儀を行うのが一般的でしたが、住宅事情の変化などから斎場での葬儀が主流となりました。
しかし近年、形式にとらわれず、故人との最後の時間を大切にしたいというニーズが高まり、アットホームな雰囲気で見送ることができる自宅での家族葬が再び注目されています。ご家族や親しい方々に囲まれて、思い出の詰まった空間で心ゆくまでお別れができる、温かみのある葬儀形式です。
家族葬を自宅で行うメリット

自宅で家族葬を行うことには、斎場での葬儀にはない多くの利点があります。ここでは、主なメリットを3つご紹介します。
【関連記事】初めてでも安心!家族葬のやり方と流れを時系列で解説【準備リスト付】 | 家族葬のそうえん【公式】 | 東京都日野、町田の葬儀社 | 多摩地区クチコミ評価No.1
メリット1:時間の制約なく故人と過ごせる
斎場やセレモニーホールを利用する場合、次の予約が入っているなどの理由で、お通夜や告別式の時間が厳密に決められていることがほとんどです。ゆっくりと故人を偲ぶ時間が十分に取れないこともあります。その点、自宅であれば時間の制約がありません。夜通し故人に付き添ったり、思い出話を語り合ったりと、ご家族のペースで心ゆくまで最後の時間を過ごすことができます。
メリット2:斎場の利用料がかからず費用を抑えられる
葬儀費用の中で大きな割合を占めるのが、斎場の使用料です。都心部や規模の大きな斎場では、数十万円の費用がかかることも珍しくありません。 自宅を式場として利用すれば、この斎場使用料が一切かからなくなります。浮いた費用を祭壇のお花や料理に充てるなど、故人やご家族が望む形でお金を使えるため、費用を抑えつつ満足度の高いお見送りを実現しやすくなります。
メリット3:思い出の詰まった自宅でリラックスして見送れる
故人にとって最も安らげる場所であったご自宅は、ご遺族にとっても心が落ち着く空間です。慣れない場所での葬儀は、気を張ってしまい精神的に疲れてしまうこともありますが、住み慣れた自宅であれば、リラックスした気持ちで故人を見送ることができます。また、ご高齢の親族や小さなお子様がいる場合でも、周りに気兼ねすることなく、体力的な負担を軽減しながら参列できるという利点もあります。
家族葬を自宅で行う際のデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、自宅で家族葬を行うためには、事前に確認し、準備しておくべき点もいくつか存在します。後悔しないために、デメリットと注意点をしっかりと把握しておきましょう。
デメリット1:ご遺体の安置や祭壇のためのスペース確保が必要
自宅で葬儀を行うには、まずご遺体を安置し、枕飾りや祭壇を設置するためのスペースを確保する必要があります。一般的に、最低でも6畳ほどの広さが必要とされています。また、参列者の人数によっては、それ以上のスペースや僧侶の控室なども考慮しなければなりません。家具の移動や片付けが必要になる場合もあるため、事前に間取りを確認し、葬儀社と相談しながらレイアウトを決めることが大切です。
デメリット2:近隣住民への事前説明と配慮が不可欠
葬儀当日は、ご遺族や参列者、葬儀社のスタッフ、僧侶など、多くの人が出入りします。また、霊柩車や送迎の車なども駐車するため、近隣住民の方々の生活に影響を与えてしまう可能性があります。トラブルを避けるためにも、事前に近隣の方々へ葬儀を執り行う旨を伝え、理解を得ておくことが重要です。「ご迷惑をおかけしますが」と一言挨拶をしておくだけで、心象は大きく変わります。駐車スペースの確保についても、事前に検討しておきましょう。
デメリット3:準備や片付けが遺族の負担になる
斎場での葬儀では、会場の設営や片付け、参列者の案内などをスタッフに任せることができます。しかし、自宅葬の場合は、これらの準備や後片付けを遺族が中心となって行わなければなりません。もちろん、葬儀社がサポートしてくれますが、自宅の清掃や家具の移動、お茶出しの準備など、ご遺族の負担は斎場で行う場合よりも大きくなる傾向があります。誰が何を担当するのか、親族間で事前に話し合っておくとスムーズです。
デメリット4:マンションの場合は管理規約の確認が必須
マンションなどの集合住宅で自宅葬を検討する場合、まず管理規約を確認することが必須です。規約によっては、ご遺体の搬入や葬儀そのものが禁止されている場合があります。 また、規約で許可されていても、棺をエレベーターや階段で搬入・搬出できるかという物理的な問題もクリアしなければなりません。事前に管理組合や大家さんに相談し、許可を得てから準備を進めるようにしましょう。
【費用】自宅での家族葬にかかる料金の内訳と相場

自宅での家族葬は斎場使用料がかからない分、費用を抑えやすいですが、具体的にどのような費用が必要になるのでしょうか。ここでは、費用の内訳と一般的な相場について解説します。
費用項目 | 内容 | 費用の目安 |
葬儀一式費用 | 搬送、安置、棺、骨壺、ドライアイス、枕飾り、祭壇、遺影、運営スタッフ人件費など、葬儀を行うために最低限必要な物品やサービスの費用。 | 15万円~30万円 |
飲食接待費用 | 通夜振る舞いや精進落としなどの飲食代、返礼品の費用。 参列者の人数によって変動する。 | 10万円~30万円 |
寺院費用 | 僧侶にお渡しするお布施(読経料、戒名料、御車代、御膳料など)。 宗派や寺院との関係性によって大きく異なる。 | 10万円~35万円 |
合計 |
| 35万円~95万円 |
上記の表はあくまで一般的な目安です。葬儀の規模や内容、依頼する葬儀社によって費用は大きく変動します。複数の葬儀社から見積もりを取り、内容をよく比較検討することが重要です。
【関連記事】【家族葬の費用】相場と内訳を徹底解説!賢く安くする方法も紹介【家族葬の費用】相場と内訳を徹底解説!賢く安くする方法も紹介
葬儀一式費用(棺、骨壺、人件費など)
葬儀を執り行う上で基本となる費用です。ご遺体の搬送や安置に必要な物品、棺や骨壺、祭壇、遺影写真の作成、そして葬儀の運営をサポートするスタッフの人件費などが含まれます。多くの葬儀社では、これらの項目をまとめた「家族葬プラン」を用意しています。プランによって含まれる内容が異なるため、どこまでがプラン内で、何が追加費用になるのかを事前にしっかり確認しましょう。
飲食接待費用
お通夜の後に参列者へ振る舞う「通夜振る舞い」や、火葬後に行う「精進落とし」といった会食の費用、そして参列者へお渡しする返礼品の費用です。自宅葬では、仕出し弁当を頼んだり、ご家族で手料理を用意したりと、形式を自由に選べます。参列者の人数や予算に合わせて柔軟に対応できるのが自宅葬のメリットの一つです。
寺院費用(お布施)
仏式の葬儀を行う場合に、僧侶へお渡しするお礼がお布施です。読経や戒名に対する謝礼としてお渡しするもので、決まった金額はありません。しかし、寺院や地域によって目安となる金額がある場合が多いため、不安な場合は葬儀社や寺院に直接尋ねてみても失礼にはあたりません。「お気持ちで」と言われた場合でも、葬儀社に相談すれば一般的な相場を教えてもらえます。
【関連記事】家族葬のお布施費用はいくら?相場と内訳、失礼のない渡し方のマナーを解説します | 家族葬のそうえん【公式】 | 東京都日野、町田の葬儀社 | 多摩地区クチコミ評価No.1
自宅で想い想いの空間を「そうたく」

住み慣れたご自宅で、故人様らしい温かいお別れを実現する自宅葬プラン「そうたく」。葬援では、ご家族の想いに寄り添い、お迎えから安置、通夜、告別式、出棺、火葬まで一貫してサポートいたします。「不明な点にすぐ対応してくださり、不安なく当日を迎えることができました」「希望に合うように工夫してくださり、アットホームな形で表現できました」とご利用者様からも高い評価をいただいております。インターネットランキング1位、口コミでも選ばれる葬援だからこそ、ご家族の希望に合わせたオリジナルなプランをご提案できます。故人様との大切な時間を、慣れ親しんだ自宅でゆっくりと過ごしませんか。
【流れ】ご逝去から葬儀後までの手順

実際に自宅で家族葬を行う場合、どのような流れで進んでいくのでしょうか。ご逝去から葬儀後までの一般的な手順を6つのステップに分けて解説します。
手順1:ご遺体の搬送・安置
病院などでお亡くなりになった場合、まずは葬儀社に連絡をします。葬儀社が寝台車でご自宅までご遺体を搬送してくれます。ご自宅に到着後、お部屋にご遺体を安置し、枕元にお線香やろうそく、お花などを飾る「枕飾り」を設置します。
手順2:葬儀社との打ち合わせ
ご遺体の安置が終わったら、葬儀社の担当者と具体的な葬儀内容の打ち合わせを行います。喪主を誰にするか、葬儀の日程、参列者の人数、祭壇の種類、遺影写真の選定など、詳細を決めていきます。この時に、費用に関する見積もりもしっかりと確認しましょう。
手順3:納棺の儀
お通夜の前に、故人のお体を清め、死装束を着せて棺に納める「納棺の儀」を執り行います。ご家族が故人と触れ合える最後の時間です。故人が生前愛用していた服を着せたり、愛用品を一緒に納めたりすることもできます(燃えないものは不可)。
手順4:お通夜
祭壇の準備が整ったら、僧侶をお迎えし、お通夜を執り行います。僧侶による読経、ご遺族・参列者による焼香という流れが一般的です。お通夜の後は、参列者へ食事を振る舞う「通夜振る舞い」を行いますが、自宅葬の場合は省略したり、軽食のみにしたりすることも可能です。
手順5:葬儀・告別式、出棺
お通夜の翌日に、葬儀・告別式を執り行います。お通夜と同様に、読経と焼香が中心となります。告別式の最後には、故人と最後のお別れをし、棺にお花などを手向けます。その後、棺をご自宅から霊柩車へ運び、火葬場へと向かいます。
手順6:火葬とお骨上げ
火葬場に到着後、火葬炉の前で最後のお別れ(納めの式)を行い、火葬となります。火葬には1〜2時間ほどかかりますので、その間は控室で待ちます。火葬が終わると、ご遺骨を骨壺に納める「お骨上げ」を行い、一連の儀式は終了となります。
自宅での家族葬を成功させる葬儀社の選び方

自宅での家族葬は、斎場で行う葬儀とは異なるノウハウが必要です。そのため、どの葬儀社に依頼するかは非常に重要になります。ここでは、信頼できる葬儀社を選ぶための3つのポイントをご紹介します。
自宅葬の実績が豊富か
まず最も重要なのが、自宅での葬儀の実績が豊富にあるかどうかです。自宅葬では、限られたスペースを有効に活用するレイアウトの提案力や、近隣への配慮、搬入・搬出のスムーズさなど、専門的なスキルが求められます。葬儀社のホームページで実績を確認したり、相談の際に自宅葬の経験が豊富か直接質問したりしてみましょう。具体的な事例を交えて説明してくれる葬儀社であれば、安心して任せることができます。
見積もりの内容が明瞭で分かりやすいか
葬儀費用は分かりにくい点も多いため、「一式」や「プラン」といった言葉だけで判断せず、見積もりの内訳を詳細に確認することが大切です。「何が含まれていて、何が追加料金になるのか」を一つひとつ丁寧に説明してくれる葬儀社を選びましょう。こちらの質問に対して、誠実に分かりやすく回答してくれるかどうかが、信頼できる葬儀社を見極めるポイントになります。
親身になって相談に乗ってくれるか
ご遺族は、悲しみや不安の中で葬儀の準備を進めなければなりません。そんな時に、事務的な対応ではなく、ご遺族の気持ちに寄り添い、親身になって相談に乗ってくれるスタッフがいる葬儀社は心強い存在です。「故人らしいお見送りにしたい」「費用を抑えたい」といった様々な要望に対して、柔軟な提案をしてくれるかどうかを見極めましょう。電話での対応や事前相談の際のスタッフの態度も、重要な判断材料になります。
【関連記事】事前相談の重要性とは | 家族葬のそうえん【公式】 | 東京都日野、町田の葬儀社 | 多摩地区クチコミ評価No.1
まとめ

自宅での家族葬は、故人が住み慣れた温かい空間で、ご家族のペースでゆっくりとお別れができる素晴らしい葬儀の形です。費用を抑えられるというメリットもありますが、スペースの確保や近隣への配慮など、事前に準備すべき点も存在します。後悔のないお見送りを実現するためには、自宅葬のメリット・デメリットをよく理解し、信頼できる葬儀社と協力しながら準備を進めることが何よりも大切です。この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、故人との最後の時間を心穏やかに過ごすための一助となれば幸いです。
「そうえん倶楽部」の生前会員制度なら、資料請求するだけで特別割引が自動適用されます!年会費・更新費・積立金は一切不要で、二親等のご親族まで追加料金なしでご利用可能です。簡単 1 分の資料請求で、安心の葬儀準備を始めませんか?
スマホの場合は、電話での問い合わせも可能です。特にお急ぎの方はお電話でお気軽にご相談ください。

厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
遺体感染管理士出身の新潟で広告業などを経験し、出産・子育てを経て東京へ移住。
縁あって出合った司会の仕事をきっかけに葬儀業界へ、年間300件のお別れに立ち会い、2021年、株式会社 葬援の取締役に就任。