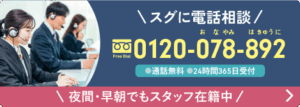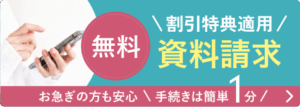身内が亡くなり、家族葬の準備を進める中で「お坊さんへのお布施はいくら包めばいいのだろう?」「失礼のないように渡すにはどうすれば?」といった疑問や不安を抱えていないでしょうか。この記事では、家族葬におけるお布施の費用相場から内訳、そして準備や渡し方のマナーまで、必要な情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、費用に関する不安が解消され、自信を持って故人様とのお別れに臨めるようになります。
家族葬でもお坊さんを呼ぶならお布施は必要

家族葬は、家族や親しい友人のみで行う小規模な葬儀形式ですが、仏式の儀式を執り行うのであれば、お坊さん(僧侶)を呼び、お経をあげていただきます。その際、感謝の気持ちとしてお布施をお渡しするのがマナーです。
お布施は読経や戒名に対する感謝の気持ち
お布施は、サービスへの対価や料金ではありません。故人を弔い、供養していただいたことに対する感謝の気持ちを示す「財施(ざいせ)」という仏教の修行の一つです。そのため、金額に明確な決まりはありませんが、感謝の気持ちを形として示すために金銭をお渡しする習慣が根付いています。お寺の運営を支えるという意味合いも含まれています。
家族葬と一般葬でお布施の金額は変わらない
家族葬は参列者が少ないため、葬儀全体の費用は一般葬に比べて抑えられる傾向にあります。しかし、お坊さんにお願いする儀式の内容(読経や戒名の授与など)は、葬儀の規模によって変わるものではありません。したがって、お坊さんにお渡しするお布施の金額は、家族葬であっても一般葬であっても、基本的には同額と考えるのが一般的です。
【内部リンク】家族葬を 5 人で行う費用はいくら?平均相場と内訳、安く抑える 7 つの方法を解説し ます
家族葬のお布施の費用相場は15万円〜50万円

お布施の金額に決まりはありませんが、ある程度の目安となる相場は存在します。この相場は、地域、宗派、そして授かる戒名の位によって変動します。不安な場合は、親族や葬儀社の担当者に相談してみるのが良いでしょう。
【一覧表】お布施の全国平均と地域別の相場
地域による文化や慣習の違いは、お布施の相場にも影響を与えます。一般的に、都市部よりも地方の方が高くなる傾向が見られます。
地域 | お布施の費用相場 |
全国平均 | 約23万円 |
北海道・東北地方 | 約31万円 |
関東地方 | 約29万円 |
中部地方 | 約25万円~27万円 |
近畿地方 | 約21万円~24万円 |
中国・四国地方 | 約20~21万円 |
九州地方 | 約17万円~22万円 |
※あくまで目安であり、寺院との関係性によっても異なります。
宗派によっても費用相場は異なる
所属する宗派によっても、お布施の考え方や相場は異なります。例えば、浄土真宗では戒名(法名)にランクがないため、他の宗派に比べてお布施が比較的安い傾向にあると言われています。一方で、歴史ある寺院や格式を重んじる宗派では、相場が高くなることもあります。
戒名のランクがお布施の金額を大きく左右する
お布施の金額を決定する最も大きな要因が「戒名」です。戒名には位(ランク)があり、故人の生前の功績や信仰の深さなどによって授けられます。一般的に、位が高くなるほどお布施の金額も高くなります。
戒名の位(下から上位へ) | 戒名料の目安 |
信士(しんじ)・信女(しんにょ) | 20万円~50万円 |
居士(こじ)・大姉(だいし) | 50万円~70万円 |
院信士(いんしんじ)・院信女(いんしんにょ) | 30万円~100万円 |
院居士(いんこじ)・院大姉(いんだいし) | 100万円以上 |
どの位の戒名を授かるかは、菩提寺がある場合は住職と相談して決めるのが一般的です。
お布施の主な内訳は「読経料」と「戒名料」

一般的に「お布施」として一括りでお渡しする金銭には、主に「読経料」と「戒名料」という2つの意味合いが含まれています。
読経料:お経をあげていただくお礼
読経料は、通夜や葬儀・告別式などでお経を読んでいただいたことに対するお礼です。枕経(臨終直後に行う読経)を含め、お坊さんが儀式で拘束される時間や日数に応じて変動します。一般的には15万円から30万円程度が目安とされています。
戒名料:仏弟子となった証である名前のお礼
戒名料は、故人に仏様の世界での新しい名前である「戒名」を授けていただいたことに対するお礼です。前述の通り、戒名の位によって金額が大きく変わるため、お布施全体の額に最も影響を与える部分です。
お布施とは別に用意すべき費用

費用を別途用意する必要があります。これらは感謝の気持ちであるお布施とは性質が異なるため、別の封筒に用意するのがマナーです。
御車代:会場までの交通費
お坊さんに葬儀会場まで足を運んでいただいた際の交通費として「御車代」をお渡しします。相場は5,000円から1万円程度です。もしご自身が車で送迎する場合や、タクシーを手配した場合は不要です。
御膳料:会食を辞退された場合のお食事代
葬儀後に行われる会食(精進落としなど)にお坊さんが参加されない場合に、食事の代わりとして「御膳料」をお渡しします。相場は5,000円から2万円程度です。会食自体を行わない場合でも、お渡しするのが一般的です。
【準備編】お布施を包む際のマナー

お布施を用意する際には、いくつかのマナーがあります。相手への感謝と敬意を示すためにも、しっかりと確認しておきましょう。
お金は新札を用意するのが望ましい
お布施は、不幸を予測して準備する香典とは異なり、あくまでも感謝の気持ちを表すものです。そのため、できる限り新札を用意するのが望ましいとされています。もし新札が用意できない場合でも、なるべく綺麗で折り目の少ないお札を選びましょう。
奉書紙か白無地の封筒を使う
お布施は、奉書紙(ほうしょがみ)という和紙で包むのが最も丁寧な方法です。しかし、用意が難しい場合は、郵便番号欄のない真っ白な無地の封筒で代用しても問題ありません。「不幸が重なる」ことを連想させる二重封筒は避けましょう。
お札は肖像画が表の上側になるように入れる
封筒にお札を入れる際は、封筒の表側(「お布施」と書かれた面)にお札の肖像画が向くように入れます。そして、封筒を開けたときに、最初に肖像画が見えるように、上向きに揃えて入れましょう。
【書き方編】お布施の封筒の書き方

お布施を入れる封筒の書き方にも決まった作法があります。薄墨ではなく、濃い墨の筆や筆ペンを使用するのがマナーです。
表書きは濃い墨の筆ペンで「お布施」と書く
封筒の表面、中央上段に「御布施」または「お布施」と書きます。その真下に、喪主のフルネーム、あるいは「〇〇家」と家名を書きます。
通常の漢数字 | 旧漢字(大字) |
一 | 壱 |
二 | 弐 |
三 | 参 |
五 | 伍 |
十 | 拾 |
万 | 萬 |
円 | 圓 |
中袋の裏面には住所と氏名を書く
中袋の裏面の左下には、喪主の住所と氏名を記入します。お寺側が整理しやすくなるように、郵便番号から正確に書きましょう。中袋がない封筒の場合は、封筒の裏面に直接、住所と金額を記入します。
【渡し方編】失礼にならないお布施の渡し方

準備したお布施は、適切なタイミングと作法で渡すことが大切です。
渡すタイミングは葬儀の開始前か終了後
お布施を渡すタイミングに厳密な決まりはありませんが、一般的には、葬儀が始まる前にお坊さんへ挨拶に伺う際か、葬儀が無事に終わって一息ついたタイミングでお渡しするのがスムーズです。慌ただしい中で渡すのは避けましょう。
必ず袱紗(ふくさ)か切手盆に乗せて渡す
お布施を直接手渡しするのはマナー違反です。袱紗(ふくさ)と呼ばれる布に包んで持参し、渡す直前に袱紗から取り出して、折りたたんだ袱紗の上に乗せて差し出します。もし葬儀社が用意してくれる場合は、切手盆(きってぼん)という小さなお盆に乗せて渡しましょう。
感謝の言葉を添えて渡すのが大切
お布施をお渡しする際は、必ず感謝の言葉を添えます。葬儀前であれば「本日は、どうぞよろしくお願いいたします」、葬儀後であれば「本日は、心のこもったお勤めをいただき、誠にありがとうございました」といったように、状況に合わせた挨拶をしましょう。
家族葬のお布施に関するよくある質問

ここでは、家族葬のお布施に関して多くの方が抱く疑問にお答えします。
菩提寺がない場合はどうすればよいですか?
菩提寺(先祖代々お世話になっているお寺)がない場合は、葬儀社に相談してお坊さんを紹介してもらうのが一般的です。多くの葬儀社では、さまざまな宗派のお坊さんを手配するサービスを提供しています。その場合のお布施の金額は、葬儀社が定めたプラン料金に含まれていることもありますので、事前に確認しましょう
お布施の費用を抑える方法はありますか?
お布施は感謝の気持ちであるため、一概に「安くする」という考え方は馴染みませんが、費用を抑えたい場合は、授かる戒名の位について相談してみるのが一つの方法です。また、菩提寺がない場合は、お坊さん手配サービスを利用すると、お布施の金額が明確に提示されていることが多く、予算が立てやすいでしょう。
お布施を渡すのを忘れた場合はどうしたらよいですか?
万が一、葬儀当日にお布施を渡しそびれてしまった場合は、気づいた時点ですぐに葬儀社かお寺に連絡を入れましょう。後日、改めてお寺に直接伺い、お詫びの言葉とともにお渡しするのが丁寧な対応です。
まとめ:相場とマナーを理解し、心を込めて感謝を伝えましょう

家族葬におけるお坊さんへのお布施は、故人を供養していただいたことへの大切な感謝のしるしです。費用相場はあくまで目安であり、最も重要なのは心を込めて感謝を伝えることです。この記事で解説した相場や内訳、そしてマナーを参考に、自信をもって準備を進めてください。費用や作法に関する不安を解消し、心穏やかに故人様との最期の時間をお過ごしください。
「そうえん倶楽部」の生前会員制度なら、資料請求するだけで特別割引が自動適用されます!年会費・更新費・積立金は一切不要で、二親等のご親族まで追加料金なしでご利用可能です。簡単 1 分の資料請求で、安心の葬儀準備を始めませんか?
スマホの場合は、電話での問い合わせも可能です。特にお急ぎの方はお電話でお気軽にご相談ください。

厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
遺体感染管理士出身の新潟で広告業などを経験し、出産・子育てを経て東京へ移住。
縁あって出合った司会の仕事をきっかけに葬儀業界へ、年間300件のお別れに立ち会い、2021年、株式会社 葬援の取締役に就任。