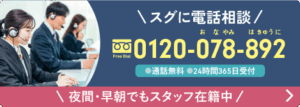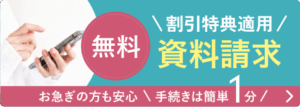ご家族が亡くなられ、葬儀の準備を進める中で「湯灌(ゆかん)はどうされますか?」と葬儀社から尋ねられ、戸惑われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。聞き慣れない言葉であり、費用もかかるため、本当に必要なのか判断に迷うのは当然のことです。
この記事では、湯灌とはどのような儀式なのか、その意味や目的、具体的な流れや費用について分かりやすく解説します。故人にとっても、ご遺族にとっても後悔のないお別れをするために、湯灌を行うべきかどうかの判断材料としてお役立てください。
記事の目次
湯灌(ゆかん)は必要?目的や重要な役割とは?

湯灌(ゆかん)とは、故人のお体を洗い清め、来世への旅立ちの準備を整える儀式のことです。単にご遺体を清潔にするだけでなく、故人への深い敬意と愛情を示すための大切な時間とされています。
湯灌の持つ3つの意味と目的
湯灌には、大きく分けて3つの意味と目的があります。
- 衛生的・身体的なケア
ご遺体を洗い清めることで、衛生状態を保つ。また、お湯で温めることで死後硬直を和らげ、安らかな表情に整える効果も期待できる。 - 宗教的・精神的な意味
仏教では、現世での悩みや穢れ(けがれ)を洗い流し、清らかな状態で来世へ旅立てるように、という願いが込められている。また、赤ちゃんが生まれて初めて浸かる「産湯(うぶゆ)」になぞらえ、新たな世界への生まれ変わりを願う意味合いもある。 - 遺族のグリーフケア
ご遺族が湯灌に立ち会い、故人の体に触れ、清める過程に参加することで、故人の死をゆっくりと受け入れ、心の整理をつける時間になる。最後のお世話をしてあげることで、「できる限りのことをしてあげられた」という気持ちが、深い悲しみを癒す一助となることもある。
必ずしも必要ではないが、重要な役割を持つ
現代の葬儀において、湯灌は必ず行わなければならない儀式ではありません。病院で亡くなった場合、多くは看護師によってアルコールなどで体を拭き清める「エンゼルケア(死後処置)」が行われるため、衛生面だけを考えれば必須ではないのです。
しかし、前述のように湯灌には衛生面以外の重要な役割があります。故人への感謝を伝え、尊厳を守り、ご遺族が心穏やかに故人を見送るための大切な儀式として、今も多くの方に選ばれています。
湯灌とエンゼルケア、エンバーミングとの違い
湯灌と混同されやすいものに「エンゼルケア」と「エンバーミング」があります。それぞれの違いを理解しておきましょう。
| 項目 | 湯灌(ゆかん) | エンゼルケア | エンバーミング |
| 目的 | 身体の洗浄 宗教的儀式 遺族のグリーフケア | 死後の処置 ご遺体の整容 | 長期的な腐敗防止 修復 |
| 内容 | 浴槽やシャワーで体を洗い清め、着付けや化粧を行う | 全身の清拭 医療器具の取り外し 着付け 簡単な化粧など | 血管に防腐剤を注入し、体内の血液と置き換える |
| 実施者 | 湯灌師 納棺師 | 看護師 葬儀社スタッフ | エンバーマー (専門資格者) |
| 場所 | 葬儀会館 自宅など | 病院 介護施設など | 専用の施設 |
| 儀式性 | 高い | 低い | ない |
エンゼルケアが主に医療的な観点から行われるのに対し、湯灌は故人との別れを惜しむ儀式としての側面が強いのが特徴です。エンバーミングは、ご遺体を長期間衛生的に保つための特殊な処置であり、目的が大きく異なります。
湯灌についてさらに詳しく知りたい方は下記記事もあわせてご覧ください。
【関連記事】湯灌(ゆかん)とは?費用や流れ、ご家族ができることを分かりやすく解説 | 家族葬のそうえん【公式】
湯灌の儀式が行われる場所とタイミング
湯灌を行うタイミングや場所は、ご遺族の希望や状況によって調整が可能ですが、一般的なケースを知っておくと、いざという時に落ち着いて判断できます。
納棺前のタイミングが一般的
湯灌は、ご遺体を棺に納める「納棺の儀」の前に行われるのが最も一般的です。湯灌で体を清め、身支度を整えた後、そのまま納棺へと進むことで、儀式がスムーズに進行します。
ご遺族や親族が集まる時間も一度で済むという利点もあります。ただし、特別な決まりはないため、「できるだけ早くきれいにしてあげたい」という希望があれば、ご安置後すぐに行うことも可能です。
場所は葬儀会館や自宅が中心
湯灌は、専門の設備が整った葬儀会館の湯灌室で行われることが多いです。
ご自宅にご遺体を安置している場合は、湯灌師が移動式の専用浴槽を持ち込んで行います。浴槽の設置には2~3畳ほどのスペースがあれば十分で、室内が濡れないように防水シートなどで養生するため、マンションなどでも問題なく実施できます。洗い清めた後のお湯は、専門の業者が責任を持って持ち帰ります。
湯灌にかかる費用相場と内訳

湯灌は多くの場合、葬儀の基本プランには含まれていないオプションサービスです。そのため、追加で費用が発生します。後で慌てないためにも、費用の相場や内訳を事前に把握しておくことが大切です。
【関連記事】湯灌の価格はいくら?費用相場と内訳、儀式の流れやマナーを解説 | 家族葬のそうえん【公式】
費用相場は5万円~10万円程度
湯灌にかかる費用の相場は、サービス内容によって異なりますが、一般的に5万円から10万円前後です。
専門の湯灌師や納棺師の人件費、専用機材の使用料などを含んだ金額です。アルコール綿などで体を拭き清める「古式湯灌(清拭)」の場合は比較的費用が抑えられ、専用の浴槽を使用する場合は高くなる傾向があります。
費用の内訳とサービス内容を必ず確認する
湯灌の費用には、どこまでのサービスが含まれているのかを事前に確認することが非常に重要です。一般的には、以下の内容が含まれていることが多いです。
- 洗体・洗髪:浴槽やシャワーを使用して全身を洗い清める。
- 着付け:経帷子(きょうかたびら)などの死装束に着替えさせる。
- 死化粧:故人のお顔を整え、安らかな表情になるように化粧を施す。
- 納棺:身支度を整えた後、ご遺体を棺に納める。
葬儀社によっては、死装束が別途料金であったり、納棺の儀式が別料金であったりするケースもあります。依頼する際には、必ず見積もりを取り、サービス内容の詳細を確認しましょう。
感謝を込めた湯灌なら「おんせん湯灌」
家族葬のそうえんでは、天然温泉水を使用した「おんせん湯灌」サービスを提供しています。
湯灌は単にお身体を清める作業ではなく、故人様とご遺族が最後に心を通わせる大切なコミュニケーションの時間です。生前の思い出を語りかけながら優しくお身体に触れることで、言葉にならない感謝の想いを伝えることができます。
古来より人々の心と身体を癒やしてきた天然温泉のお湯で、人生という長い旅路の疲れを癒し、清めて差し上げる。それは故人様への最後の、そして最上の贈り物となるでしょう。後悔のないお別れのために、清らかな感謝のひとときをお過ごしください。
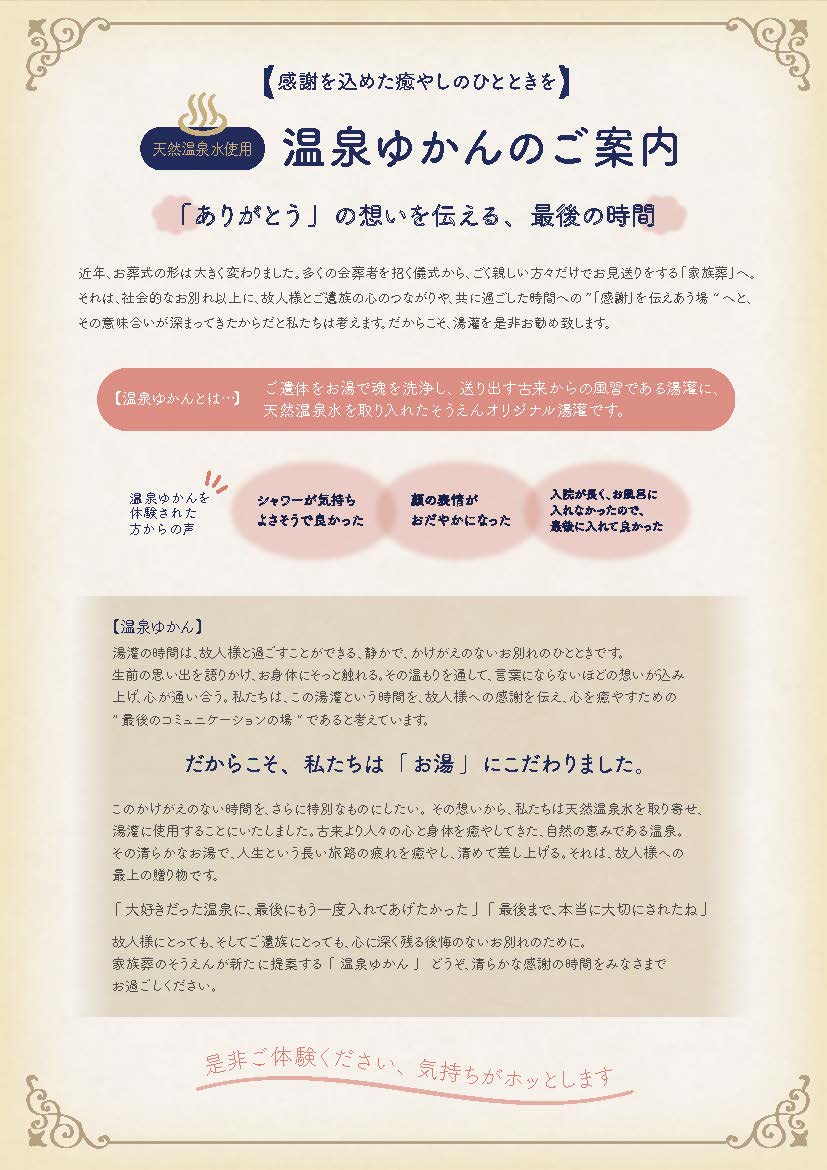
家族葬のそうえんでは、皆様に安心してご準備いただけるよう お得な会員制度(そうえん倶楽部)をご用意しております。気になる方はぜひ一度資料をご確認くださいませ。
湯灌を行うメリットとデメリット
湯灌を行うかどうかを決める際には、メリットとデメリットの両方を理解し、ご家族でよく話し合うことが重要です。故人への想いと、ご遺族の状況を総合的に考えて判断しましょう。
メリット:故人への敬意を表せ、遺族の心のケアができる
湯灌を行う最大のメリットは、故人の尊厳を守り、心を込めて送り出すことができる点です。
最後にお風呂に入れてあげたい、きれいな姿で旅立たせてあげたいというご遺族の願いを叶えることができます。また、ご遺族が湯灌の儀式に立ち会い、故人との最後の触れ合いの時間を持つことで、深い悲しみを乗り越えるための「グリーフケア」の効果も期待できます。死という現実を受け入れ、穏やかな気持ちで故人を見送るための大切なプロセスとなり得ます。
デメリット:費用負担と所要時間が発生する
一方、デメリットとして最も大きいのは、やはり費用面です。
葬儀費用全体を少しでも抑えたいと考えている場合には、5万円から10万円という追加費用は大きな負担となる可能性があります。また、湯灌には1時間から1時間半程度の時間が必要です。葬儀までの日程が限られている場合や、遠方から参列する親族の都合などによっては、時間の確保が難しいケースも考えられます。
湯灌の具体的な流れと手順
湯灌の儀式がどのように進められるのか、具体的な流れを知っておくことで、安心して立ち会うことができます。ここでは、一般的な湯灌の手順をご紹介します。
1.湯灌の準備と逆さ水の儀式
まず、湯灌師が儀式の説明を行い、故人が安置されている場所(または湯灌室)に専用の浴槽を準備します。
その後、「逆さ水(さかさみず)」の儀式を行います。通常お湯に水を足して温度を調整するのとは逆に、水にお湯を足して適温にする作法です。非日常の世界を表す「逆さごと」という習わしの一つで、故人の死を日常と切り離す意味があります。ご遺族も儀式に参加し、柄杓(ひしゃく)で故人の足元から胸元へとお湯をかけていきます。
2.洗体・洗髪と着付け・死化粧
湯灌師が、故人の肌を露わにしないようバスタオルなどで覆いながら、全身と髪を丁寧に洗い清めます。ご遺族が故人の愛用していたシャンプーなどを使用したい場合は、事前に葬儀社に相談してみましょう。
洗浄が終わると、ご遺体を清らかな布で拭き、布団へ移します。そして、経帷子(きょうかたびら)などの死装束に着替えさせます。ご遺族が手伝うことも可能です。着付けが終わると、髪を乾かし、爪を整え、お顔に死化粧を施して、生前の安らかなお顔に近づけます。
湯灌から納棺までの所要時間について
湯灌の儀式にかかる時間は、準備から納棺まで含めて、全体で1時間から1時間半程度が目安です。この後、そのまま納棺の儀へと移り、故人との思い出の品などを一緒に棺に納めます。
湯灌に立ち会う際のマナーと服装

湯灌の儀式に立ち会うことになった場合、どのような服装で、誰が参加すればよいのでしょうか。事前にマナーを知っておくと安心です。
【関連記事】湯灌の価格はいくら?費用相場と内訳、儀式の流れやマナーを解説 | 家族葬のそうえん【公式】
立ち会うのは近親者が中心になる
湯灌の儀式に立ち会う人の範囲に厳密な決まりはありませんが、故人の肌を目にすることもあるため、基本的にはご遺族やごく近しい親族のみで執り行われます。
故人のプライバシーを守るためにも、親族以外の方が立ち会う場合は、喪主の許可を得るのがマナーです。小さなお子様の立ち会いについては、精神的な影響も考慮し、ご家族で慎重に判断しましょう。
服装は平服で問題ない
湯灌に立ち会う際の服装は、喪服である必要はなく、「平服(普段着)」で問題ありません。
ただし、派手な色やデザイン、露出の多い服装は避け、黒や紺、グレーといった落ち着いた色合いの、清潔感のある服装を心がけましょう。湯灌の後にそのまま通夜が執り行われる場合は、あらかじめ喪服を着用しておくとスムーズです。
まとめ
湯灌は、故人への最後の奉仕であると同時に、残されたご遺族の心を癒すための大切な時間でもあります。しかし、必ずしも行わなければならない儀式ではありません。
湯灌を行うかどうかを判断する際には、以下の点を考慮し、ご家族でよく話し合うことが大切です。
- 故人が生前、お風呂が好きだったか
- 故人にきれいな姿で旅立ってほしいという想いが強いか
- 故人との最後の触れ合いの時間を持ちたいか
- 費用面での負担は問題ないか
- 時間的な余裕はあるか
最終的にどのような選択をするにせよ、故人を想い、ご遺族が納得して決めることが何よりも重要です。この記事が、後悔のないお別れのための一助となれば幸いです。
「そうえん倶楽部」の生前会員制度なら、資料請求するだけで特別割引が自動適用されます!年会費・更新費・積立金は一切不要で、二親等のご親族まで追加料金なしでご利用可能です。簡単1分の資料請求で、安心の葬儀準備を始めませんか?
スマホの場合は、電話での問い合わせも可能です。特にお急ぎの方はお電話でお気軽にご相談ください。

厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
遺体感染管理士出身の新潟で広告業などを経験し、出産・子育てを経て東京へ移住。
縁あって出合った司会の仕事をきっかけに葬儀業界へ、年間300件のお別れに立ち会い、2021年、株式会社 葬援の取締役に就任。