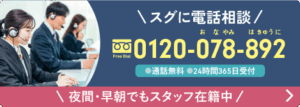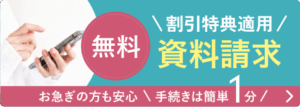近年、親しい家族や親族のみで故人様を穏やかに見送る「家族葬」を選ぶ方が増えています。
しかし、いざ自分が執り行う立場になると、「葬儀費用は一体誰が支払うのが正しいのだろうか」という疑問や不安に直面する方は少なくありません。大切な方を亡くされた悲しみの中で、費用の問題が親族間のトラブルに発展することは避けたいものです。
この記事では、家族葬の費用を誰が支払うべきかという疑問を中心に、一般的な慣習や法律上の考え方、具体的な支払い方法、そして親族間で円満に話を進めるためのポイントまで、分かりやすく解説します。
記事の目次
家族葬の費用は一般的に誰が払う?
家族葬の費用について、誰が支払うべきかという明確なルールに迷うかもしれません。
まずは、一般的な考え方と法律上の位置づけについて解説します。
原則として「喪主」が支払う
一般的に、葬儀の費用は葬儀全体を取り仕切る責任者である「喪主(もしゅ)」が支払うケースが最も多いです。喪主は、葬儀社の選定から内容の決定、費用の交渉までを行うため、支払いも喪主の名義で行うのが自然な流れとなります。
通常、故人の配偶者や長男・長女など、血縁関係が最も近い方が喪主を務めます。
法律上の支払い義務は定められていない
実は、法律において「葬儀費用は〇〇が支払わなければならない」という明確な定めはありません。誰が支払っても法的に問題はなく、あくまで慣習として喪主が支払うことが多いのが実情です。
喪主が経済的な理由で支払いが困難な場合や、親族間で合意がある場合は、他の人が支払うことも全く問題ありません。
「喪主」と「施主」の違いとは?
葬儀の話では「施主(せしゅ)」という言葉も出てきます。喪主と混同されがちですが、役割が異なります。それぞれの役割を理解しておくと、費用の話がスムーズに進みます。
| 役割 | 説明 |
| 喪主 | 遺族の代表として、葬儀全体の責任者。弔問客への対応など、儀式的な役割を主に行う。 |
| 施主 | 葬儀費用を実際に負担する人。運営面での責任者。 |
通常は「喪主」と「施主」を兼任する場合がほとんどですが、例えば喪主が高齢であったり、まだ若かったりして経済的な負担が難しい場合に、別の親族が施主となって費用を支払うことがあります。
喪主以外が費用を支払うケース

前述の通り、葬儀費用は必ずしも喪主が一人で負担する必要はありません。ここでは、喪主以外の方が費用を支払う代表的なケースを3つご紹介します。
| 支払いパターン | メリット | デメリット |
| 施主が負担 | 喪主の経済的負担をなくせる | 施主となる人の負担が大きくなる |
| 遺産から支払う | 相続人の自己負担がない | 相続人全員の合意形成が必要 |
| 子供たちで分担 | 一人当たりの負担額を軽減できる | 負担割合で揉める可能性がある |
施主が費用を負担する
喪主が儀礼的な代表者を務め、費用は別の親族(施主)が負担するケースです。
例えば、喪主は長男が務めるが、実際に費用を支払うのは経済的に余裕のある次男、といった形です。
役割を分担することで、誰も無理をすることなく、円滑に葬儀を進められます。
相続人が故人の遺産から支払う
故人が自身の葬儀費用として財産を遺している場合、その遺産から支払うのも一般的です。相続人(遺産を受け継ぐ権利のある人)全員の合意があれば可能です。
故人の遺志を尊重する形となり、特定の誰かに負担が偏ることもないため、多くのケースで選択されます。ただし、後述するように、故人の銀行口座が凍結される前に手続きについて確認しておく必要があります。
子供たちが費用を分担する
故人に複数の子供がいる場合、兄弟姉妹で費用を均等に分担する方法です。これも非常に一般的な方法であり、親族間の公平性を保ちやすいメリットがあります。
「長男だから多く出すべき」といった考えに固執せず、それぞれの経済状況なども考慮しながら、全員が納得できる割合で分担することが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。
家族葬の費用を支払うための具体的な方法
実際に費用を支払う段階になったとき、どのようなお金を充てることができるのでしょうか。ここでは、費用の工面に役立つ具体的な方法を解説します。
| 故人が加入していた保険 | 補助金の名称 | 申請先 | 給付額の目安 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療制度 | 葬祭費 | 故人の住所地の市区町村役場 | 3万円~7万円 |
| 会社の健康保険(協会けんぽなど) | 埋葬料 | 健康保険組合や社会保険事務所 | 一律5万円 |
故人の預貯金から支払う場合の手順と注意点
故人の遺産から費用を支払う場合、預貯金を引き出して利用するのが一般的です。
しかし、金融機関は名義人の死亡を知ると口座を凍結するため、注意が必要です。口座凍結後でも、一定額(上限150万円)までは「預貯金の仮払い制度」を利用して引き出すことが可能ですが、手続きに時間がかかる場合があります。
葬儀費用は葬儀後すぐに支払いを求められることが多いため、可能であれば口座が凍結される前に、相続人同士で話し合いの上、必要な金額を引き出しておく方がスムーズです。
香典を葬儀費用に充てる
参列者からいただいた香典を葬儀費用の一部に充てることも広く行われています。
ただし、家族葬の場合は参列者が少ないため、一般葬に比べて香典の総額も少なくなる傾向があります。遺族の意向で香典を辞退するケースも多いため、香典をあてにしすぎない資金計画が重要です。
生命保険の死亡保険金を活用する
故人が生命保険に加入していた場合、受取人に指定された人が死亡保険金を受け取れます。この保険金を葬儀費用に充てるケースも多いです。請求手続き後、比較的速やかに支払われる保険も多いため、大きな助けになります。
故人が保険に加入していたか分からない場合は、保険証券などを探してみましょう。
公的な補助金制度を利用する
故人が加入していた公的な健康保険から、葬儀費用の一部が補助される制度があります。申請しないと給付されないため、忘れずに手続きを行いましょう。
葬儀費用で親族と揉めないための3つのポイント

葬儀費用の話は、親族間であってもデリケートな問題です。ここでは、無用なトラブルを避け、円満に話を進めるための3つの重要なポイントをご紹介します。
| トラブル回避のポイント | 具体的なアクション |
| 事前の話し合い | 親が元気なうちに葬儀の希望や費用の負担方法について話し合う。 |
| 情報の透明化 | 葬儀の見積書を関係者全員で共有し、内容と金額を確認する。 |
| 香典のルール決め | 香典を受け取るか辞退するか、受け取る場合の使い道を事前に決めておく。 |
ポイント1:生前に誰が支払うかを話し合っておく
最も理想的なのは、親が元気なうちに、万が一の際の葬儀費用について誰がどのように負担するのかを家族で話し合っておくことです。
親自身の希望を聞き、遺産から支払うのか、子供たちで分担するのかなどを決めておけば、いざという時に慌てずに済みます。縁起でもないと感じるかもしれませんが、事前の話し合いが、残された家族の負担を大きく減らすのです。
ポイント2:葬儀の見積書を親族間で共有する
葬儀社を決め、具体的なプランの見積書が出たら、関係する親族(特に費用を分担する可能性のある人)全員で共有しましょう。
金額や内容をオープンにすることで、「何にいくらかかっているのか分からない」といった不信感をなくし、透明性を確保できます。全員が納得した上で話を進めましょう。
ポイント3:香典の取り扱いを決めておく
家族葬では香典を辞退することも多いですが、もし受け取る場合はその使い道を事前に決めておくとスムーズです。
一般的には葬儀費用に充て、残った分は喪主が受け取るか、あるいは費用を分担した人たちで分けるなどの方法があります。この点も事前に合意しておくことで、後のトラブルを未然に防げます。
家族葬にかかる費用の相場と内訳
家族葬の費用は、参列者の人数や地域、葬儀の内容によって変動しますが、ある程度の相場を知っておくことは大切です。
【関連記事】【家族葬の費用】相場と内訳を徹底解説!賢く安くする方法も紹介
家族葬の費用相場
全国的な家族葬の費用相場は、おおよそ80万円~110万円の範囲に収まることが多いです。一般葬の費用相場が160万円前後であることと比較すると、費用を抑えられる傾向にあります。
ただし、これはあくまで目安であり、選ぶプランやオプションによって金額は大きく変わります。
費用の主な内訳
葬儀費用は、主に以下の3つの要素で構成されています。この内訳を理解しておくと、見積書の内容を確認しやすくなります。
| 費用の種類 | 内容 | 費用を左右する要因 |
| 1.葬儀一式費用 | 祭壇、棺、遺影、ご遺体の搬送・安置、式場使用料、人件費など、儀式そのものに必要な費用。 | 祭壇のグレード、棺の種類、式場の規模など。 |
| 2.飲食接待費用 | 通夜振る舞いや精進落としなどの飲食代、会葬御礼品や香典返しなどの返礼品費用。 | 参列者の人数、料理のグレード、返礼品の品物。 |
| 3.寺院費用 | 読経や戒名に対するお礼として僧侶にお渡しするお布施。 | 寺院との関係性、戒名のランクなど。 |
家族葬の費用負担を抑えるための方法

大切な故人を見送る儀式ですが、できれば費用は抑えたいと考えるのは自然なことです。ここでは、葬儀の質を落とさずに費用負担を軽減するための具体的な方法をいくつかご紹介します。
| 費用を抑える方法 | メリット | 注意点 |
| 相見積もり | 適正価格を把握でき、最適なプランを選べる | 時間的な余裕が必要になる場合がある |
| 内容の見直し | 不要なオプションを削り、費用を直接的に削減できる | 家族・親族間での合意形成が必要 |
| 公営斎場の利用 | 式場使用料を大幅に削減できる | 予約が取りにくい場合がある、設備がシンプルなことが多い |
複数の葬儀社から見積もりを取る
葬儀社によって、プランの内容や料金体系は大きく異なります。時間に余裕があれば、2〜3社から同じ条件で見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。
サービス内容と費用のバランスが取れた、納得のいく葬儀社を見つけられます。
葬儀の規模や内容を見直す
費用を抑える上で最も効果的なのは、葬儀の規模や内容をシンプルにすることです。
例えば、祭壇のグレードを少し控えめにしたり、参列者の人数を絞り込むことで飲食接待費用を削減したりすることが考えられます。
故人らしさを大切にしつつ、どこにお金をかけるべきか、家族で優先順位を話し合ってみましょう。
公営斎場を利用する
葬儀を行う斎場には、民間企業が運営するものと、自治体が運営する「公営斎場」があります。
公営斎場は、民営斎場に比べて利用料金が安価に設定されていることがほとんどです。
その地域の住民であればさらに割引料金で利用できる場合も多く、費用を大幅に抑えることが可能です。
まとめ
家族葬の費用は、法律で定められているわけではありませんが、一般的には喪主が支払うことが多いです。
しかし、喪主が一人で抱え込む必要はなく、故人の遺産から支払ったり、兄弟姉妹で分担したりと、様々な方法があります。最も大切なのは、費用の問題をきっかけに親族間でわだかまりを残さないことです。
そのためには、生前の話し合いや、情報の共有を心がけ、全員が納得できる形で話を進めることが重要です。この記事が、故人様との最期の時間を心穏やかに過ごすための一助となれば幸いです。
「そうえん倶楽部」の生前会員制度なら、資料請求するだけで特別割引が自動適用されます!
年会費・更新費・積立金は一切不要で、二親等のご親族まで追加料金なしでご利用可能です。簡単1分の資料請求で、安心の葬儀準備を始めませんか?
スマホの場合は、電話での問い合わせも可能です。特にお急ぎの方はお電話でお気軽にご相談ください。

厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
遺体感染管理士出身の新潟で広告業などを経験し、出産・子育てを経て東京へ移住。
縁あって出合った司会の仕事をきっかけに葬儀業界へ、年間300件のお別れに立ち会い、2021年、株式会社 葬援の取締役に就任。